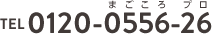滝廉太郎が「創造」した日本の西洋音楽~結核によって「解体」された音楽人生

明治時代、日本は西洋列強に「追いつけ追い越せ」を合言葉に幅広い分野での西洋文化を積極的に取り入れました。音楽もそのひとつです。
日本には古来より伝統の音楽文化があり、それは雅楽や浄瑠璃、長唄などバラエティも豊かで、庶民に至るまで根付いた文化でした。そのような状況下、明治政府は西洋音楽の普及を国策として進めたのです。
こうした国策に従って日本の西洋音楽の礎を築いた人物として滝廉太郎をご紹介しましょう。廉太郎はその儚い命を「解体」しながら、日本の西洋音楽を「創造」していったのです。
滝廉太郎と西洋音楽
滝廉太郎は1879年(明治12年)に東京で生まれました。滝家は武士の家柄で、父親は官僚として明治政府に仕えて、廉太郎の幼少期は地方を転々としながらのものでした。
廉太郎の音楽の才能は少年時代には既に開花しつつあり、当時最年少の15歳で東京音楽学校(現在の東京藝術大学)に入学します。音楽学校ではピアノ演奏と作曲についての技術を伸ばし、卒業後に数々の唱歌や童謡を世に送り出します。
「花」や「お正月」、「箱根八里」、そして代表曲である「荒城の月」など短期間に多くの曲を作りました。
これらの曲の特徴として、西洋音楽の旋律を取り入れながら、日本語の歌詞がなじむように作られていることが挙げられます。
1901年(明治34年)、21歳のときにドイツのライプツィヒ音楽院に文部省留学生として入学します。
ライプツィヒ音楽院はメンデルスゾーンが設立した名門音楽大学です。廉太郎は3カ年の予定でピアノや音楽理論について学ぶこととなります。
結核により「解体」されゆく命
ところが入学から間もなく、期待に満ちあふれた留学生活に影を落とすことになります。
音楽院に入学してわずか2ヶ月で肺結核を発病してしまったのです。
この時代、結核は「国民病」と呼ばれるほど多く見られ、当時の医療技術ではほとんど打つ手がなく、死亡率も非常に高かったのです。こうした状況は日本に限らずヨーロッパでも同様でした。
廉太郎はドイツの病院で療養しますが、改善の兆しは見られず、結局1902年(明治35年)秋に志半ばに帰国せざるを得ませんでした。
帰国後は、大分に住む両親のもとで静養しますが、翌夏23歳であまりに短い生涯を閉じます。
結核により亡くなったことから、死後多くの作品が焼却されたと言われており、現存するのは34曲のみです。
現存するなかで廉太郎が最後に病床で作曲した「憾(うらみ)」というピアノ曲には廉太郎の高い技術とともに病に倒れた無念さが強くにじんでいます。
死後「創造」された「日本の西洋音楽」、そして世界へ
文字通りその命を「解体」し、その作品の多くまでもが「解体」されてしまった廉太郎ですが、その足跡は日本の西洋音楽史のはじめの大きな一歩として残されています。
廉太郎が作曲した曲は現代でも広く親しまれ、音楽の教科書に載っていることはもちろんのこと、鉄道の発車メロディーなど街なかでも耳にする機会が多くあります。
さらに、「荒城の月」は西洋音楽の本場であるヨーロッパでも親しまれています。ベルギーのとある修道院では約30年前より聖歌として使われており、ドイツを代表するロックバンド・スコーピオンズがライブで歌唱したことも知られています。
このように海外でも知られるようになったきっかけは昭和を代表するオペラ歌手藤原義江が歌ったことだとも言われています。
滝廉太郎の洋の東西を問わず愛される音楽は「日本の西洋音楽」というジャンルを確かに「創造」したのです。
明治時代に急速に西洋文化を取り入れるために失われたものは多くあります。
自らの命を投げ打ってまで新しい日本の文化を創造するために尽力した滝廉太郎はその象徴とも言えるでしょう。
「解体」されゆく命と引き換えに「創造」された日本の西洋音楽。その儚くも力強いメロディーにいま一度耳を傾けてみてはいかがでしょうか?